1.左のおしりが痛いときに考えられる主な原因
・筋肉や神経のトラブル(梨状筋症候群・坐骨神経痛など)
・骨・関節由来の痛み(仙腸関節障害・腰椎由来の放散痛)
・内臓疾患による関連痛(尿路結石・婦人科系疾患など)
・日常生活での負荷や姿勢の問題
2.痛みの特徴からわかること|見極めのポイント
・動作で悪化する痛みかどうか
・しびれ・麻痺など神経症状の有無
・痛みの広がり方(おしり〜太もも・足先)
3.自宅でできる対処法とセルフケア
・安静と姿勢の見直し
・ストレッチ・温める方法の注意点
・市販薬や湿布の使い方と限界
4.早めに病院を受診すべき症状とは?
・痛みが長引く・強くなる
・歩行が困難になる・しびれがひどい
・発熱や排尿異常を伴う場合
・整形外科・神経内科・泌尿器科などの受診先の目安
5.再発予防のために見直したい生活習慣
・座り方・立ち方・歩き方の工夫
・骨盤周りの筋力トレーニング
・慢性化させないための定期的なケア
1.左のおしりが痛いときに考えられる主な原因

筋肉や神経のトラブル
「座ってると、左のおしりだけズーンと痛くなる…」
そんなときに多く挙げられているのが、梨状筋症候群や坐骨神経痛などの筋肉・神経系のトラブルです。特に長時間のデスクワークや運転が続くと、**おしりの奥にある筋肉(梨状筋)**が硬くなり、近くを通る神経を圧迫することがあると言われています。
その結果、おしりの痛みに加えて、太ももやふくらはぎまで「じわ~っ」としたしびれを感じることもあります。
骨・関節由来の痛み
「腰に異常はないと思うけど、なぜかおしりが痛い」
こうした症状には、仙腸関節の障害や、腰椎からくる神経の放散痛が関わっている場合もあるようです。特に、片側だけに痛みが出ることが多く、座った姿勢や寝返り時にズキッと感じることがあるのだとか。
関節のわずかなズレでも、周囲の筋肉や神経に負担がかかり、思わぬ場所に不調が出ることがあるとも言われています。
内臓疾患による関連痛
「なんとなく違和感があるけど、便秘っぽいし関係あるのかな?」
実は、おしりの痛みが内臓からのサインとして現れることもあるようです。たとえば、尿路結石や**婦人科系の疾患(卵巣・子宮周囲)**などが原因で、周囲の神経を通じて痛みが広がるケースもあるとされています。
とくに、排尿の異常や発熱などを伴う場合には注意が必要です。
日常生活での負荷や姿勢の問題
「姿勢が悪いって自覚はあるけど、まさかおしりが痛くなるなんて…」
と思われるかもしれませんが、意外と多いのが姿勢の崩れや筋力の低下による負担です。猫背や反り腰、偏った座り方などが積み重なることで、特定の部位に負担が集中してしまうとも言われています。
ちょっとしたクセでも、慢性的な筋緊張につながり、結果的に痛みが出やすくなる可能性があるようです。
#左のおしりが痛い
#梨状筋症候群
#仙腸関節障害
#坐骨神経痛の特徴
#姿勢と筋肉バランス
2.痛みの特徴からわかること|見極めのポイント
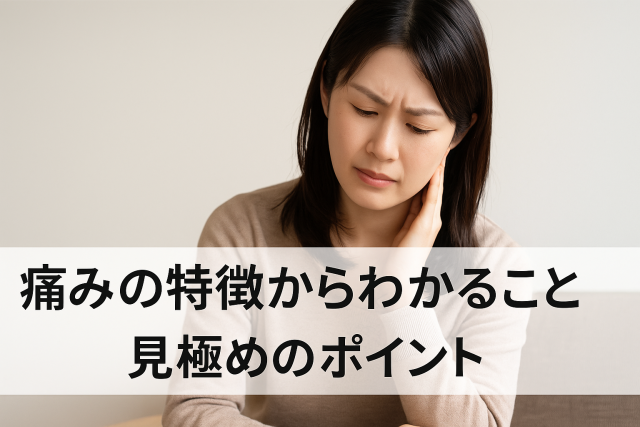
動作で悪化する痛みかどうか
「立ち上がった瞬間にズキンと痛む」「座っているとジワジワくる」
こんなふうに、動作の前後で痛みが変わる場合、筋肉や関節に負荷がかかっている可能性があると考えられています。たとえば、梨状筋症候群や仙腸関節の不具合などが挙げられます。
特に、長時間同じ姿勢を取ったあとに痛みが強くなるケースでは、筋肉のこわばりや関節のズレが影響していると言われています。
一方、安静時でも痛みが消えないような場合は、別の原因が考えられることもあるため、慎重な観察が必要とされています。
しびれ・麻痺など神経症状の有無
「おしりが痛いだけじゃなく、なんだか足先もしびれてきた…」
こんな症状が出ているときは、神経の圧迫が関係している可能性があるります。
典型的なのは、坐骨神経痛や椎間板ヘルニアなどで、腰からおしり、脚へと広がる神経のどこかでトラブルが起きていることがあるようです。
神経症状が出ていると、感覚が鈍くなったり、動かしづらさを感じることもあるとされており、自己判断で放置しないことが重要です。
痛みの広がり方(おしり〜太もも・足先)
「左のおしりが痛いと思っていたのに、気づいたら太ももまで…」
こうした“痛みの広がり方”も、原因を見極めるための大事なヒントになってくるようです。
筋肉の痛みだけであれば、比較的局所的にとどまることが多いですが、坐骨神経痛など神経が関係する場合には、足の後ろ側全体に痛みやしびれが広がるケースがあるとされています。
また、痛みの範囲が日によって変わる、場所が移動するような感覚があるときは、体のバランスの乱れや複数要因が絡んでいることも考えられるようです。
#左のおしりが痛い
#痛みの広がりと見極め
#坐骨神経痛のサイン
#神経圧迫の可能性
#しびれと動作の関係
3.自宅でできる応急的な対処法と生活での注意点

安静にするべきか、動かすべきかの判断
「この痛み、動かさないほうがいいのかな…?」
そう感じる方も多いのではないでしょうか。基本的に、痛みが強く出ているときは無理に動かさず、安静を保つことが大切だと考えられています。ただし、まったく動かさないでいると筋力が落ちてしまうこともあるため、痛みがやわらいだタイミングでゆっくり動かすようにするのが良いとも言われています。
温める or 冷やす?症状による使い分け
「冷やすべき?それとも温めるべき?」
この判断、意外と迷いますよね。急に痛みが出たばかりのときや、炎症っぽい腫れがある場合は冷やすのが望ましいとされています。一方で、慢性的にこわばっている・冷えると悪化するような痛みには温めるほうがよいと言われています。
どちらか迷ったときは、「冷やして痛みが増すか、温めて楽になるか」を体感で見極めるのも1つの方法かもしれません。
ストレッチやマッサージはしてもいい?
「少し動かしたほうが楽になる気がするけど…大丈夫かな?」
軽いストレッチやマッサージは、症状が落ち着いてきた段階で行うのが望ましいとされています。特におしりまわりの筋肉(梨状筋など)は硬くなりやすく、適度にほぐしてあげると楽になることもあるようです。
ただし、無理に伸ばしたり押したりするのは逆効果になることもあるため、力加減には注意が必要です。
長時間の座位や負荷がかかる動作を避ける工夫
同じ姿勢を続けることは、痛みを悪化させる要因のひとつと言われています。とくに、長時間のデスクワークや運転などは要注意。
30分に一度、立ち上がって軽く体を動かす習慣を取り入れると、体への負担を軽減できるかもしれません。
#痛みのセルフケア
#冷やすか温めるか
#安静か運動かの判断
#ストレッチとマッサージ
#生活習慣と姿勢の見直し
4.病院に行くべき症状と来院のタイミング
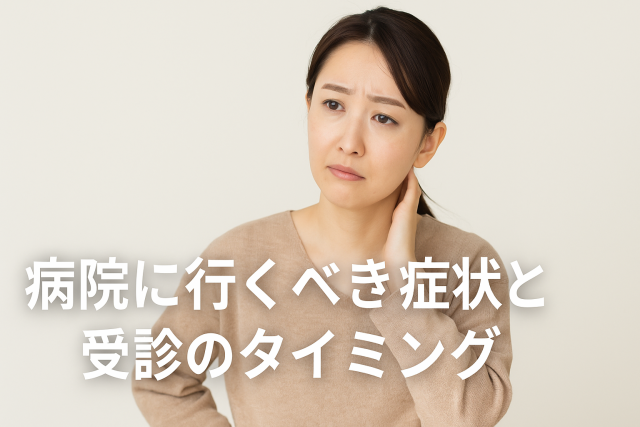
痛みの特徴からわかること|見極めのポイント
「なんとなく痛いけど、このまま様子見てて大丈夫かな…?」そう思いながら放置してしまう方、けっこう多いんです。
でも、ある程度の見極めポイントを知っておくだけでも、適切なタイミングで来院しやすくなるかもしれません。
痛みが強くなる・長引くときの対応
軽い違和感で始まったとしても、徐々に痛みが強くなったり、1週間以上改善が見られないときは注意が必要だと言われています。
特に日常生活に支障が出ている場合には、整形外科などで一度検査を受けておくと安心かもしれません。
しびれや筋力低下を伴う場合の注意点
「足にしびれがある」「踏ん張りがきかない」といった症状があると、坐骨神経などへの影響が考慮されます。
神経が関係している場合は、自然に改善するケースもあれば、早めの施術が推奨される場合もあります。
内臓の問題を疑うべき症状
実は、お尻や腰の痛みが内臓からの関連痛である可能性もあるとされています。例えば、婦人科系の不調や泌尿器の異常が影響するケースもあるようです。
痛みと同時に、排尿の違和感や周期的な腹部の張りがある場合などは、婦人科や内科を検討することがすすめられる場面もあります。
整形外科・神経内科・婦人科の選び方
どの診療科に行けばいいか迷ったら、まずは痛みの部位や症状の種類で判断してみましょう。
・体を動かしたときに痛む → 整形外科
・しびれや感覚異常が目立つ → 神経内科
・月経や内臓の症状と関連 → 婦人科
こうした傾向があると言われていますが、迷ったときはまず整形外科で検査を受けてから専門科に紹介してもらう方法もあります。
#まとめ
#痛みが続くときの対処
#しびれや力が入らない症状
#内臓との関連を疑うサイン
#整形外科と神経内科の違い
#婦人科に行くべきタイミング
5.再発予防のために見直したい生活習慣とセルフケア

再発予防のために見直したい生活習慣とセルフケア
「もう二度と、あの痛みは繰り返したくない…」
そう感じたこと、ありませんか?つらい症状が改善したあとこそ、普段の生活の中でできることを意識しておくと、再発リスクを減らすことができるとも言われています。
正しい姿勢と座り方の習慣化
おしりや腰の痛みを繰り返す方の多くに、姿勢の崩れや座り方のクセがあるとも言われています。
特に、背もたれに深く腰掛けずに前かがみになっていると、骨盤が後傾して筋肉に余計な負担がかかることがあるようです。
イスに座るときは「坐骨で支える」「膝は90度」といったポイントを意識すると良いかもしれません。
おしりや骨盤まわりの筋力トレーニング
「筋力が落ちていると、体を支えきれない」といった話もよく聞きます。
おしり(大臀筋)や内もも(内転筋)、腹横筋など体幹を支える筋肉を軽く鍛えておくと、骨盤が安定しやすくなると考えられています。
スクワットやブリッジといった動きは、負荷が少なくて続けやすいとも言われています。
冷えやストレスによる悪化を防ぐ工夫
冷たい床で長時間座っていたり、ストレスがたまっているときに痛みが再発しやすい…そんな経験はないでしょうか?
冷えは血流の低下につながるため、温かい服装や入浴習慣を見直すことがすすめられています。また、ストレス管理の一環として深呼吸や軽い運動を取り入れる方も増えているようです。
日常で取り入れたいストレッチや体操
「疲れたときほど、ちょっと伸ばすと楽になる」と感じる人も多いようです。
おしりや太もも、股関節まわりのストレッチは、筋肉を柔らかく保つために役立つとされています。
ラジオ体操のような軽い動きでも、こまめに体を動かす意識が習慣化につながるかもしれません。
#まとめ
#姿勢改善で再発予防
#おしりと骨盤の筋トレ
#冷え対策とリラックス習慣
#日常にストレッチを取り入れる
#セルフケアの意識づけ
この記事に関する関連記事
- 右のおしりが痛い|原因・考えられる病気と自分でできるケア方法
- 太ももの裏の筋が痛い時に知っておきたい原因と対策ガイド|武庫之荘駅前整骨院サキュレ
- 坐骨結節 痛み 原因:座ってもズキッとくる理由と対策ガイド
- 左臀部 痛み の原因と対策|片側だけ痛む時にまず知っておくべきこと
- 「坐骨神経痛ストレッチ即効ガイド – 今すぐできる3分ケアで痛みを和らげる」
- 坐骨神経痛 やってはいけないこと|痛みを悪化させる5つのNG行動と正しい対処法
- 坐骨神経痛 治療方法|症状別に選ぶ最新の治療法とセルフケアのポイント
- 左股関節の痛みを感じたら?考えられる原因と対処法を解説
- うつ伏せで腰が痛い?ヘルニアとの関係と正しい対処法を解説
- 足の付け根と腰が痛い原因とは?考えられる疾患と対処法を解説
- 坐骨神経痛 しびれ:原因から対処法まで徹底解説!
- 坐骨神経痛 スクワット 悪化を防ぐ!正しいフォームと注意点を徹底解説
- ヘルニア 足のしびれ ストレッチ|自宅でできる簡単ケアで症状の緩和を目指そう
- 【坐骨神経痛でやってはいけないこと】整体院に行く判断基準は❓







お電話ありがとうございます、
武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。