【記事構成】
1五十肩の症状とは?(夜間痛・動作制限・生活への影響)
・夜寝返りでの激痛、梳頭・着脱での痛みなどの具体的な症状
・自分で腕を挙げられない、他人に補助しても不可能といった診断目安
2症状の進行ステージと期間:疼痛期→僵硬期→回復期
・各ステージの特徴と目安期間(疼痛期:6週~9ヶ月/僵硬期:4~9ヶ月/回復期:5ヶ月~2年など)
・ステージごとの症状変化(痛みの変化、可動域の制限など)
3原因と高リスク群:なぜ五十肩になるのか?
・関節囊の炎症・線維化・癒着のメカニズム
・年齢(40~60代)、女性、糖尿病・甲状腺疾患・術後不動などのリスク要因
4セルフチェックと診断ポイント
・セルフテスト例:梳頭・背中に手が回るか・対側肩への手の動かしにくさなど
・主動・他動運動ともに制限される点が五十肩の特徴で、肩袖損傷などとの鑑別にもなる
5治療とケア:リハビリ・専門的治療・自然経過
・自然経過:放置だと1~3年かかり、40%は残存症状あり
・治療選択肢:NSAIDs、ステロイド注射、物理療法(熱・電・レーザー)、リハビリ運動
・進行例への対応:震波療法、関節囊拡張術、徒手療法など
・継続的なストレッチや運動の重要性とその効果
1. 膝の新常識”とは?
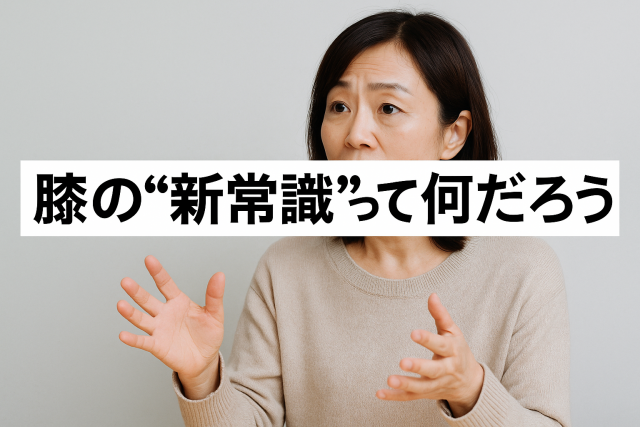
膝の“新常識”って?
普通は、変形性膝関節症って聞くと『軟骨がすり減ると痛い』ってイメージだと思いますがでも実は違います。
その驚きの研究の背景は?
「MRIとかも使って膝の状態を詳しく見ます。軟骨がほとんど残ってない人でも、『正座できる』『歩ける』『痛みがない』って人がいます。」
それだけじゃなくて、軟骨には神経がないから、削れても痛みを感じないこともあります。むしろ、痛みの原因って軟骨ではなくて、関節包や靭帯などの“軟部組織”だったりする場合もあります。
#変形性関節症
#変形性膝関節症
#軟骨だけが原因ではない
#東京医科歯科大学新潟大学研究員
#膝の痛みの新常識
2変形性膝関節症の基礎知識:症状や進行ステージを押さえる

変形性膝関節症の基礎知識
「膝が痛いと年齢のせいかなって思うこと、ありますよね?」
この症状は、膝の軟骨がすり減ったり、炎症が起きたりして関節に負担がかかることで進行していきます。軟骨そのものは神経がないから直接痛みを感じるわけではありませんが、周囲の組織に炎症が広がると強い痛みが出たりします。関節が変形してくると動きにも制限が出やすくなります。
進行ステージごとの特徴とは?
初期段階:膝に違和感が出て、階段を降りる時に痛みを感じることが増える。まだ軽いから休めば落ち着く人もいる。
中期段階:軟骨がさらに減り、立ち上がりや歩行の最初の一歩がつらいと感じやすい。膝に腫れが出る場合もある。
進行期:膝の変形が進み、正座やしゃがむ動作が困難になる。痛みが続き、夜間にも響くことがある。
末期段階:軟骨がほとんど残っていない状態で、膝の可動域が大きく制限される。生活全般に支障をきたすケースが多い。
「軟骨が減っても痛くない人」もいれば、「早い段階から強い痛みを感じる人」もいます。だからこそ、自分の膝の状態を正しく知っておくことがとても大切です。
#変形性膝関節症
#膝の痛み
#進行ステージ
#軟骨と炎症
#基礎知識
3なぜ“軟骨がなくても動ける”?痛みの本当の原因を科学的に読む

痛みの本当の原因とは?
実は軟骨には神経がないから、直接的には痛みを感じません。
むしろ痛みの大きな要因は、関節包や靭帯、筋肉などの“軟部組織”にあると考えられています。
炎症がそこに起きることで神経が刺激され、痛みを感じるケースが多いです。
さらに最近は心理的な影響や中枢神経の働きも関係しているといわれています例えば「膝が悪いに違いない」と思い込むことで痛みが強まることも。
日本整形外科学会の見解でも「痛みの発生には複数の要因が絡む」と説明されていて、軟骨の摩耗だけに注目するのは不十分だとされています。
つまり、膝の痛みは“軟骨の減少=痛み”ではなく、多角的にとらえる必要があります。
#変形性関節症
#変形性膝関節症
#軟骨と痛みの関係
#日本整形外科学会
#痛みの本当の原因
4自宅でできるケアと生活習慣の工夫

ウォーキングのポイント
一番取り入れやすいのはウォーキングです。
ただし注意点があり、いきなり長時間歩くのは膝に負担がかかるので、まずは10分程度から始めるのが安心です。
靴はクッション性のあるものを選ぶと膝への衝撃が減るし、アスファルトより公園の土の道を歩くほうが優しいです。
スクワットはやり方次第
実は正しいフォームなら大腿四頭筋を鍛えるのに最適です。
膝を深く曲げすぎないこと、つま先より前に膝が出ないよう意識することが大切です。
浅めに腰を落とす“ハーフスクワット”なら、膝にやさしく筋力アップが期待できます。
膝にやさしいトレーニングと生活習慣
ウォーキングやスクワットのほかにも、膝まわりの筋肉を意識した軽い運動が効果的です。
太ももの前側(大腿四頭筋)を強くする「椅子に座って片足を伸ばす運動」などは、自宅でも簡単にできます。体重管理も大切で、体重が1kg減ると膝への負担は3〜4kg分軽くなるとも言われています。
さらに温めるケアも血流を良くして痛みを和らげやすいです。
#変形性膝関節症
#自宅でできるケア
#膝にやさしい運動
#ウォーキングとスクワット
#生活習慣改善
5いつ専門家に相談すべき?

まずは検査から
「相談したら、いきなり手術になるのでは」と不安に思う人も多いです。
でも実際は、まず問診や触診をして膝の状態を把握することから始まります。
必要に応じてX線やMRIなどの画像検査を行い、軟骨や骨、関節の状態を詳しく確認します。
ここで“どのステージにあるか”をしっかり知ることが、その後の方針を決めるうえでとても重要になります。
保存療法から手術までの選択肢
治療の流れは大きく二つに分かれます。初期から中期では保存療法が基本です。
例えば、リハビリで筋肉を鍛えたり、膝への負担を減らすための生活指導、関節内注射などが行われます。
一方で、保存療法で効果が不十分な場合や、痛みが強くて生活に支障がある場合には手術という選択肢が出てきます。
関節鏡を使って関節内をきれいにする方法や、骨の角度を整える高位脛骨骨切り術、そして人工膝関節置換術といった方法があります。
#変形性膝関節症
#専門医に相談
#保存療法と手術
#膝の検査の大切さ
#生活を守る選択
この記事に関する関連記事
- 膝 伸ばすと痛い時の原因と自宅ケア+専門受診のタイミング
- 膝が痛い時の原因と対策|痛みを抑えるセルフケア+受診目安ガイド
- 膝の外側が痛い 急に感じたらまず知るべき5つの原因と対処法
- 鵞足炎 治し方|症状を和らげるセルフケア・ストレッチと治療法を解説
- 膝 内側 痛みがつらいときに考えられる原因と正しい対処法・受診の目安
- 股関節痛いと感じたら?考えられる原因と今すぐできる対処法・受診の目安
- 膝の皿の下痛いと感じたら?考えられる原因と対処法を解説
- 膝ついたら痛い原因とは?考えられる疾患と対処法を解説
- 背骨 歪みが引き起こす体調不良とは?原因と改善方法を徹底解説
- 膝が重い・違和感の原因とは?考えられる疾患と対処法を解説







お電話ありがとうございます、
武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。