【記事構成】
1 症状別に知る:寝不足で起こる“片頭痛”と“緊張型頭痛”
・片頭痛:「片側ズキズキ、光や音に敏感、吐き気を伴う」などの症状説明 。
・緊張型:「後頭部から首にかけて重苦しさ、締め付け感」 。
2 痛みにはこれ!即効セルフケア(片頭痛=冷やす/緊張型=温める)
・片頭痛:冷却シート・保冷剤・氷嚢で冷やす、光・音を避け、暗い静かな場所へ逃げる 。
・緊張型:首・肩を蒸しタオルで温める、お風呂でゆっくり温める、軽いストレッチ 。
3 すぐできる!ツボ押しでラクになる
・百会・頷厭・風池・天柱・肩井など、押し方・回数の具体手順付き 。
4 次に備える:睡眠の質を上げて頭痛予防
・規則正しい就寝起床、朝日を浴びる、寝室環境の整備(暗さ、静かさ、温度) 。
・寝具の見直し、ブルーライトの対策、入浴タイミング・方法。
5 どうしても痛いときの対処と受診目安
・市販鎮痛薬の使い方(適量・使用頻度の注意、薬物乱用頭痛への言及) 。
・起床時の慢性頭痛・原因不明の場合は専門医受診を促す(睡眠時無呼吸、脳疾患など) 。
1症状別に知る:寝不足で起こる“片頭痛”と“緊張型頭痛”
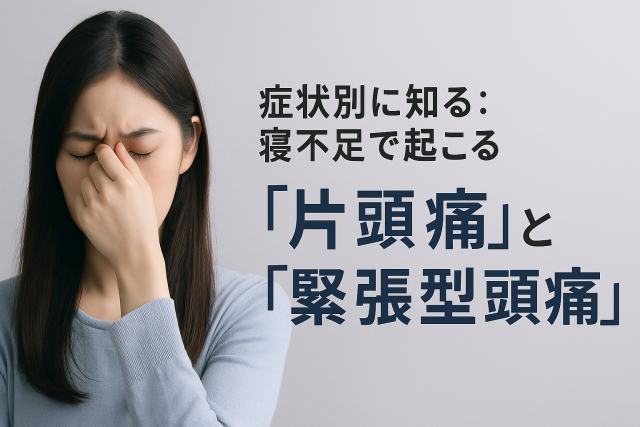
片頭痛の特徴とは
「寝不足で頭がズキズキすることってある?」と聞かれると、多くの人が思い当たるかもしれません。
実はその痛み、片頭痛である可能性があります。
片頭痛は片側のこめかみや後頭部が強く脈打つように痛むのが特徴で、光や音に敏感になったり、吐き気を伴ったりすることも少なくありません。
特に寝不足や寝過ぎといった睡眠リズムの乱れは、片頭痛を引き起こす大きな要因といわれています。
「夜更かしをした翌日に痛みが出る」というケースもよくある話で、体が悲鳴をあげているサインともいえるでしょう。
緊張型頭痛の特徴とは
一方で、「頭が締め付けられるように重い」「首から後頭部にかけてじわじわ痛む」といった症状は、緊張型頭痛が考えられます。
こちらは長時間のデスクワークやスマホ操作、姿勢の乱れなどで筋肉がこわばり、血流が悪くなることで起こることが多いとされています。
寝不足もまた、筋肉の緊張を強める要因のひとつです。
「仕事でパソコンに向かい続けたあとに、ズーンと重たい感じがする」という経験がある人は、このタイプの頭痛を抱えている可能性が高いといえます。
片頭痛と緊張型の見分け方
ではどうやって見分ければいいのでしょうか。
簡単にいうと、脈打つような痛みで吐き気や光への敏感さがあれば片頭痛、締め付けるような重苦しさがあれば緊張型頭痛の傾向が強いと考えられます。
ただし、人によって症状が重なって出ることもあるので、ひとつの目安として捉えるのがよいでしょう。
「この前はズキズキしたけど、今日は重だるい…」というように、日ごとに変化する場合もあるため、日常の記録をつけると違いが見えやすくなります。
日常生活への影響
どちらの頭痛も放っておくと集中力が途切れやすくなり、日常生活や仕事のパフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。
寝不足が続くと体の疲れも取れにくく、頭痛が慢性化するリスクもあるため、まずは自分の症状を知り、適切なケアにつなげることが大切です。
#寝不足頭痛
#片頭痛と緊張型頭痛
#睡眠不足の影響
#セルフチェック
#頭痛改善の第一歩
2痛みにはこれ!即効セルフケア(片頭痛=冷やす/緊張型=温める)

片頭痛のセルフケア:冷やして静かに過ごす
「ズキズキする片頭痛の時はどうしたらいい?」という声をよく耳にします。
片頭痛の場合は、血管が拡張している影響で痛みが強まると考えられており、冷やすことで落ち着きやすいといわれています。
冷却シートや保冷剤をタオルで包んで、こめかみや後頭部にあてるとスッと楽になることもありますね。
また、光や音の刺激が痛みを悪化させることがあるため、カーテンを閉めた暗めの部屋で静かに横になるのも一つの方法です。
実際に「冷やして横になったら楽になった」という声も少なくありません。
緊張型頭痛のセルフケア:温めてほぐす
一方で、後頭部から首にかけて重たいような痛みが続く緊張型頭痛では、血行の滞りや筋肉のこわばりが関わっていることが多いといわれます。
そのため、冷やすのではなく温めることが大切です。
蒸しタオルを首や肩にのせてみたり、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かると血流が良くなり、気持ちも落ち着きやすくなります。
さらに、肩回しや首を軽く伸ばすストレッチを取り入れることで、筋肉の緊張が和らいで痛みが軽減するケースもあります。
「お風呂上がりにストレッチをすると楽になる」という体験を話す人もいるほどです。
自分の頭痛タイプを見極めてケアを選ぶ
片頭痛と緊張型頭痛では、正反対のケアが有効になるケースがあります。
「冷やすのか?温めるのか?」を間違えると、かえって不調が長引くこともあるため、自分の頭痛タイプを意識して対応することが大切です。
どちらの痛みでも、強い症状が続いたり、いつもと違う感覚を覚えたときには無理をせず専門機関への来院を検討することも安心につながります。
普段の生活の中で「今日は冷やした方がいいのか、温めた方がいいのか」を意識するだけでも、痛みのコントロールに役立ちやすいのです。
#ぎっくり頭痛対策
#片頭痛セルフケア
#緊張型頭痛ケア
#冷やすか温めるか
#生活に役立つ健康習慣
3すぐできる!ツボ押しでラクになる

頭痛に効くツボの基本
「頭が重くてつらい時、薬に頼る前にちょっと試せる方法はないかな?」そんなふうに思ったことはありませんか。
実はツボ押しは、自宅や職場でもすぐにできるセルフケアの一つです。手軽さに加え、副作用の心配が少ないことも魅力です。
ここでは代表的なツボを紹介し、押し方や回数を具体的にお伝えします。
百会(ひゃくえ)
頭のてっぺん、耳と鼻を結んだラインの交わるあたりにあるツボです。
両手の中指を重ねて、ゆっくり息を吐きながら5秒ほど押し込みます。
これを3~5回繰り返すと、ぼんやりとした重さが和らぐ感覚を得やすいといわれています。
頷厭(がんえん)
こめかみの少し上、口を開けると動く部分にあるツボです。
人差し指や中指で軽く円を描くように5秒ずつ押し、3回ほど繰り返してみましょう。
片頭痛のズキズキ感を落ち着かせたいときに役立つとされています。
風池(ふうち)と天柱(てんちゅう)
首の後ろ、髪の生え際の少し内側にある2つのツボです。
親指を使って頭の重さを支えるようにしながら、じんわり10秒ほど押します。血流の巡りを整えるサポートとなり、首や肩のこわばりにもアプローチできます。
肩井(けんせい)
肩の一番盛り上がった部分にあるツボです。
反対側の中指や人差し指で強すぎない圧を加え、10秒程度を3回ほど。肩や首からくる緊張型頭痛のときに、スッと楽になる感覚を覚える人も少なくありません。
#寝不足頭痛
#ツボ押しセルフケア
#片頭痛緊張型対策
#自宅でできる改善法
#頭痛予防のヒント
4次に備える:睡眠の質を上げて頭痛予防」

睡眠リズムを整えることが頭痛予防につながる
「頭痛が出やすいのは寝不足のせいかも?」と感じたことはありませんか。
実際、睡眠の乱れは片頭痛や緊張型頭痛の誘因になりやすいといわれています。
まず意識したいのは、就寝と起床の時間をなるべく一定にすること。
休日も含めて同じリズムを保つことで、体内時計が整い、頭痛が起こりにくい状態を維持しやすくなります。
また、朝にカーテンを開けて太陽の光を浴びると、脳がしっかりと目覚め、自然と夜の眠りも深まりやすくなるのです。
寝室環境を工夫して安眠をサポート
「寝室の明るさや温度って関係ある?」と思う人も多いでしょう。
頭痛を防ぐには、眠りの質を上げる環境づくりも大切です。
部屋を暗くして静かな環境を整えることに加え、エアコンや加湿器を使って快適な温度・湿度に保つのも有効です。
寝具を見直すのも一つの方法で、自分の体に合った枕やマットレスを選ぶだけでも睡眠の深さが変わることがあります。
「寝具を変えてから朝がすっきりするようになった」という声も少なくありません。
ブルーライト対策や入浴習慣でリラックス
スマホやパソコンを寝る直前まで使っていると、ブルーライトの影響で眠りが浅くなるケースがあります。
できれば就寝の1時間前には画面から離れ、照明も暖色系に切り替えると安心です。
また、入浴のタイミングも重要で、就寝の1〜2時間前にぬるめのお風呂に浸かると体温がゆるやかに下がり、自然に眠りに入りやすくなります。
お湯の温度は熱すぎない方がリラックスにつながりやすいので、じんわり温まる程度を意識してみるとよいでしょう。
#頭痛予防
#睡眠の質改善
#寝室環境整備
#ブルーライト対策
#快眠習慣
5どうしても痛いときの対処と受診目安

市販薬の使い方と注意点
「頭がガンガンして、どうにもならないときはどうしたらいい?」と相談されることがあります。
そんなときに手を伸ばしやすいのが市販の鎮痛薬です。
薬は適量であれば一時的に痛みを和らげてくれる心強い存在です。
ただし注意が必要で、決められた用量や間隔を守らずに飲み続けると“薬物乱用頭痛”と呼ばれる別の症状を引き起こす恐れがあるといわれています。
「飲めば楽になるから」と毎日のように使ってしまうのは避けたいところです。
あくまでも一時的なサポートとして利用し、基本は休養や生活リズムの見直しと組み合わせるのが安心です。
専門医の来院が望ましいケース
では、どんなときに専門医へ来院したほうがよいのでしょうか。
例えば、朝起きたときから頭痛が続いている、何週間も痛みが改善しない、または強い吐き気やしびれを伴う場合は注意が必要です。
睡眠時無呼吸症候群や脳の疾患が背景に隠れている可能性もあります。
こうしたケースでは自己判断をせず、医療機関で触診や検査を受けて原因を確認してもらうことが大切です。
自分でできる判断の目安
「少し休めば楽になる」程度ならセルフケアでも十分ですが、「生活に支障が出るほど続く」「普段と違う痛み方をしている」といったサインがあれば専門家に相談したほうが安心です。
友人や家族に「その頭痛、ちょっと気になるよ」と声をかけられたときも、放置せずに早めの行動につなげたいところです。
#寝不足頭痛
#市販薬の正しい使い方
#薬物乱用頭痛に注意
#専門医来院の目安
#慢性頭痛のサイン
この記事に関する関連記事
- 運動すると頭痛になる原因とは?対処法と予防のポイント
- こめかみが痛い時に知っておきたい原因と改善法〜セルフケアから受診の目安まで〜
- つらい頭痛を自宅でケアする5つのステップ|武庫之荘駅前整骨院サキュレ
- 「頭がジーンとする」原因と対処法|放置しないためのチェックリスト付き完全ガイド
- 頭痛 吐き気 対処:すぐできるセルフケアと危険サインの見分け方
- 「頭が痛い 対処法:タイプ別・原因別にすぐできる対処ガイド」
- 頭痛い時の対処法|すぐできる緩和ケアと危険なサインの見分け方
- しゃがむと頭痛がするのはなぜ?考えられる原因と見逃せない危険サイン
- 頭が痛い 対処法|タイプ別に学ぶ正しいケアと予防法
- 寝違えた 首痛い時の正しい対処法と予防策|専門家が解説
- 頭痛治し方|タイプ別の原因と効果的な対処法を徹底解説
- 【頭痛の原因 / 頭痛薬を使わない治療法】







お電話ありがとうございます、
武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。