【記事構成】
1頭痛の種類と原因を知ろう
→ 緊張型頭痛・片頭痛・群発頭痛などの特徴と、原因(姿勢・ストレス・血管拡張など)を整理。
2まず今日すぐできるセルフケア法
→ 冷やす/温める、ツボ押し、ストレッチ、暗い静かな環境など、症状が出たときの対処法。
3頭痛を予防するための生活習慣改善
→ 睡眠・食事・水分・姿勢・目の疲れ・ストレス管理など、日常で気をつけるポイント。
4セルフケアで改善しないとき・危険サインを見逃さない
→ 頭痛が頻繁・強い・突然・麻痺・発熱を伴うなどの場合の受診目安。
5頭痛別に効く具体テクニック&ツール紹介
→ 緊張型と片頭痛それぞれに有効なツボ・体操・市販薬の利用の仕方・専門医の活用について。
1頭痛の種類と原因を知ろう

主な3種類の頭痛とは?
緊張型頭痛
このタイプは、肩・首のこりや長時間のデスクワーク、スマホ操作などで首筋が固まったり、目の疲れがたまったりして起こることが多いです。頭がギューッと締め付けられるような重さ・圧迫感が特徴。痛み自体は激痛とまではいかないことが多いですが、毎日だったり長時間だったり続くケースもあります。
片頭痛
一方で、片頭痛はズキンズキンと脈打つような痛みを伴うことが多く、頭の片側が痛くなったり、光や音、においに敏感になったり、吐き気が出ることも。20~40代の女性に特に多く見られます。痛みの持続時間も数時間~数日ということもあり、日常生活に支障をきたすことも。
群発頭痛
そして群発頭痛。これはややマイナーながら、かなり激しい痛みを伴います。目の奥がえぐられるような痛み、涙や鼻水・鼻づまりなど自律神経が反応する症状も出やすいです。発症頻度は少ないですが、発作期が来ると毎日のように痛みに襲われる期間があります。
それぞれの原因をざっくり整理
緊張型頭痛:首・肩まわりの筋肉の緊張やコリが血流を妨げることで起こることが多いです。長時間の同じ姿勢、目の疲れ、精神的・肉体的ストレスがきっかけになることも。
片頭痛:血管が「拡張」し、炎症が起きると考えられています。寝不足・寝すぎ・空腹・ストレス・気候の変動・飲酒・特定の食品など、さまざまな誘因があります。
群発頭痛:こちらは特に自律神経の関与が強いとされ、三叉神経刺激や視床下部の変化などが関わっている可能性も。誘因としてはアルコールや喫煙、睡眠パターンの乱れなども挙げられています。
#頭痛の原因
#片頭痛対策
#緊張型頭痛
#群発頭痛とは
#日常ケアで改善
2まず今日すぐできるセルフケア法

① 冷やす・温めるで刺激をコントロール
「冷やすのと温めるの、どっちがいいの?」とよく聞かれますが、痛みの出方によって使い分けがポイントです。ズキズキと拍動するような痛みがある場合は、冷たいタオルや保冷剤をタオル越しに当てると、血管の拡張を抑えて落ち着きやすくなります。逆に、首や肩こりが原因でじわじわ重い痛みがあるときは、蒸しタオルなどで温めると血流が促され、筋肉の緊張がやわらぎます。
② ツボ押しでこわばりをほぐす
手軽にできる方法として、ツボ刺激も役立ちます。こめかみの少し後ろにある「太陽」や、親指と人差し指の骨の間にある「合谷」は、ゆっくり押すと頭まわりの緊張を緩めるといわれています。力を入れすぎず、「気持ちいい」と感じる強さで10〜15秒ほど押すのがコツです。
③ 軽いストレッチで血流を促す
デスクワークやスマホ操作が続いたときは、首や肩まわりの筋肉が硬くなって痛みを悪化させることがあります。深呼吸しながらゆっくり首を回したり、肩を上下に動かすだけでも、血流の滞りが改善しやすくなります。無理に引っ張らず、「気持ちいい範囲」で行うことが大切です。
④ 静かな環境で脳を休ませる
音や光の刺激がつらいときは、暗く静かな場所で目を閉じて過ごすだけでも体が休まります。カーテンを閉めて照明を落とし、深呼吸を意識するだけでも神経が落ち着き、症状がやわらぐことがあります。「ちょっと横になるだけ」でも、思った以上に効果を感じられる人も少なくありません。
#セルフケア
#頭痛対策
#ツボ刺激
#ストレッチ習慣
#静かな環境
3頭痛を予防するための生活習慣改善
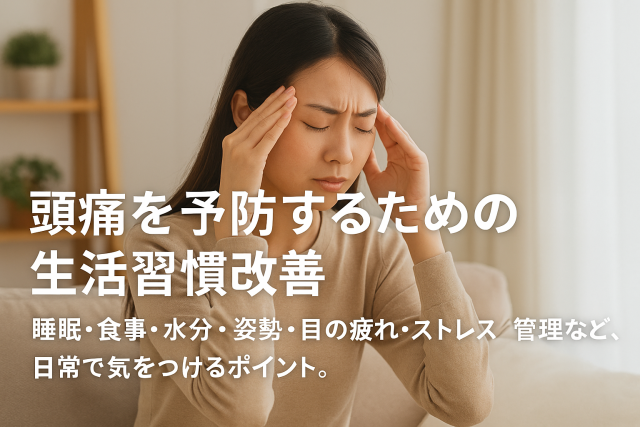
睡眠は“質”がカギ。夜更かしを減らしてリズムを整える
睡眠不足や不規則な生活は、頭痛の引き金になりやすい大きな要因です。
「つい夜遅くまでスマホを見てしまう…」という人は、就寝の1時間前から画面を見るのを控え、部屋を暗めにするだけでも睡眠の質が上がりやすくなります。朝起きる時間を一定にすることも、自律神経の乱れを防ぐコツです。
食事と水分で“頭痛を起こしにくい体”をつくる
朝食を抜いたり、カフェインをとりすぎたりすると、血管や神経のバランスが崩れやすくなります。
野菜・たんぱく質・炭水化物をバランスよくとること、1日1.5〜2ℓを目安に水分をこまめにとることが大切です。「喉が渇いてから飲む」では遅いので、少量をこまめに意識してみましょう。
姿勢と目の疲れは“慢性頭痛”の隠れ原因
デスクワークが多い人は、猫背や前傾姿勢が首まわりの筋肉をこわばらせ、緊張型頭痛を起こすことがあります。
1時間に1回は立ち上がって体を伸ばす、画面の高さを目線と同じにするなど、環境の工夫が有効です。
また、長時間のスマホ・PC作業は目の疲れも原因になるため、「20分見たら20秒遠くを見る」ルールを意識すると良いでしょう。
ストレスとの付き合い方を工夫して“心”も軽く
心の緊張やプレッシャーは、体の緊張と同じように頭痛の誘因になります。
仕事の合間に深呼吸をする、趣味の時間をつくるなど、自分なりのリセット方法を持っておくと安心です。
「頑張りすぎない」ことが、結果的に体を守ることにもつながります。
#生活習慣改善
#頭痛予防
#睡眠と姿勢
#ストレスケア
#水分と食事
4セルフケアで改善しないとき・危険サインを見逃さない

頭痛が長引く・強まるときは要注意
「市販薬で落ち着くと思ってたのに、何日も続く…」そんなときは、体からのサインを見逃さないことが大切です。特に、週に何度も頭痛が出る、日常生活に支障が出るほど強いなどの場合は、自己ケアだけで様子を見るのは避けた方がいいかもしれません。
突然”の激しい痛みはすぐ専門機関へ
「今までと違う」「バットで殴られたような痛みが急に来た」――そんなケースは、脳や血管のトラブルが関係している可能性も考えられます。たとえ一時的に落ち着いても、念のため早めに医療機関に相談することが安心です。
麻痺・しびれ・言葉の出づらさは赤信号
頭痛に加えて手足の麻痺や口の動かしにくさ、ろれつが回らないといった神経症状があるときは、脳への影響が起きている可能性があります。放置せず、できるだけ早く専門家のチェックを受けましょう。
発熱・吐き気・視覚異常があるときも注意
単なる頭痛と思っていても、発熱や吐き気、視界のかすみなどが伴う場合は、感染や炎症、眼や内臓との関連も否定できません。特に症状が重なっているときは、早期の対応が改善につながることがあります。
#頭痛の危険サイン
#突然の激痛
#麻痺やしびれに注意
#発熱や吐き気を伴う
#早めの相談が安心
5頭痛別に効く具体テクニック&ツール紹介
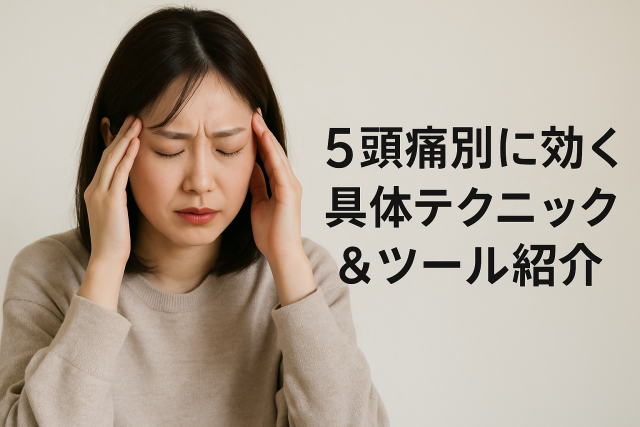
緊張型頭痛に効くケア
ツボ押し:「風池(ふうち)」と呼ばれる後頭部のくぼみを、深呼吸しながらじんわり押してみてください。目の疲れにもつながって楽になります。
簡単体操:両肩をすくめてストンと落とす動きを10回ほど繰り返すだけでも、首〜肩の筋肉がゆるみやすくなります。
市販薬の使い方:筋緊張に伴う痛みには、鎮痛剤を一時的に使う選択肢もありますが、連用は避けて。目安や服用法は必ず添付文書をチェックしましょう。
片頭痛への対処
ツボと冷却:「太陽(たいよう)」と呼ばれるこめかみ付近を軽く押すと楽になる人も多く、冷たいタオルで冷やすと拡張した血管が落ち着きやすくなります。
動かない勇気:無理なストレッチや運動は逆効果になる場合も。静かな部屋で休むことが、結果的に早い改善につながることがあります。
薬と専門家:片頭痛向けの専用薬も市販されていますが、頻度が高いときは専門医に相談を。触診や検査で別の原因が見つかることもあります。
#頭痛対策
#緊張型頭痛ケア
#片頭痛の工夫
#セルフケア習慣
#専門医相談のコツ







お電話ありがとうございます、
武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。