1.足の裏の外側が痛いときに考えられる主な原因とは?

まずは日常の行動を振り返ってみましょう
「最近、足の裏の外側がズキッとすることが増えてきた…」
そんな声、実はよく耳にします。特に、歩きすぎた日や新しい靴を履いたときに違和感が出やすいようです。
足に合わない靴や長時間の歩行によって、外側の足裏に負担が集中することがあり、それが痛みにつながる可能性があるとも言われています。
「履き慣れた靴なのに」と感じる方もいますが、靴底のすり減りやインソールの劣化など、見落としがちな要素が原因になっていることもあるようです。
筋肉や腱の炎症が関係しているケースも
足の外側には、腓骨筋(ひこつきん)と呼ばれる筋肉があり、ここが繰り返し刺激を受けることで炎症を起こすことがあります。
「特に運動をした記憶がないのに…」という方でも、知らず知らずのうちに体重のかけ方にクセがある場合、それが積み重なって痛みとして表れることもあるようです。
無理にストレッチやマッサージをしてしまうと、かえって悪化することもあります。違和感が続くときは、まず安静にして様子を見ることが大切とされています。
足のバランスが崩れているかもしれません
「外反母趾や偏平足とは無縁だと思ってた」という方でも、足の骨格がわずかにズレていることは意外とあるようです。
足のアライメント(骨格の配列)が乱れていると、外側に余計な負荷がかかるようになるといった意見もあります【引用元:https://tokyo-seikeigeka.jp/blog/17415/】。
たとえば、歩くときに足の外側ばかりで着地しているような場合、足裏の特定の部位だけにダメージが蓄積することもあるようです。
神経のトラブルが隠れている可能性も
あまり知られていませんが、足の神経が刺激されたり圧迫されたりすることで、足裏の外側にピリピリした痛みが生じるケースもあります。
「モートン病」などがその一例として挙げられるようで、指の付け根や外側アーチに症状が出ることも報告されています【引用元:https://takada-seikei.jp/column/ashinoitami-mortonbyo.html】。
もしも「しびれを感じる」「触れていないのに痛い」といった症状がある場合、神経系の関与も視野に入れる必要があります。
#足裏の痛み
#腓骨筋腱炎
#足の外側が痛い
#モートン病
#靴選びの見直し
2.痛みの場所別に見る症状の特徴とチェックポイント

外側アーチやかかと寄りが痛いときは?
「足の裏の外側がズーンと重だるい…特にかかとに近い場所が気になる」
そんな風に感じる方は意外と多いです。このあたりの痛みは、歩行時の着地衝撃が集中するエリアなので、疲労が蓄積しやすいと言われています。
特に外側アーチにそって違和感が出ている場合、足のアライメント(骨格の配列)や、腓骨筋への負担が関係している可能性があるようです。
「歩きすぎたかな?」と気づくきっかけになるのも、この辺りの痛みが出てからということも少なくありません。
小指の下や足の外側に局所的な痛みがあるとき
「足の小指の下の方、ちょうど床に当たるところがズキズキするんだけど…」
こんな声もよく聞かれます。
小指の付け根付近や足の外側に限定された痛みは、靴の締めつけや圧迫によるものとも考えられています。
とくにヒールや細めのスニーカーなど、横幅に余裕がない靴を長時間履いた後に痛むという方もいらっしゃいます。
また、外側の骨(第5中足骨)にストレスがかかり続けることで炎症が起きるケースもあるようです【引用元:https://tokyo-seikeigeka.jp/blog/17415/】。
つま先立ち・歩行・着地時、それぞれの違いに注目
「歩くときより、つま先立ちすると痛いかも」
あるいは「地面に足をついた瞬間にピリッとくる」など、動作によって痛みの出方が違う場合もあります。
たとえば、つま先立ちで痛む場合は、足底筋や腱への負担が関係しているとされ、逆に着地時に鋭い痛みが走るような場合は、骨や神経への影響も疑われるといった見解があります【引用元:https://takada-seikei.jp/column/ashinoitami-mortonbyo.html】。
体重のかけ方によっても違いが出るため、どんな動作で痛みを感じるのかを意識することで、原因のヒントが得られるかもしれません。
神経や靴の形状も関係しているかも?
実は、足の裏の外側に出る痛みには、神経の圧迫や刺激が関わっているケースも報告されています。
モートン病などがその代表例とされており、神経が圧迫されるとしびれやピリピリ感が現れることがあるそうです。
また、足を圧迫するような靴を履いていると、それ自体が刺激となって神経を過敏にする場合もあるようです。「お気に入りの靴を履いた日は痛みが出やすい」と感じる場合は、靴のフィット感を見直すタイミングかもしれません。
#足裏の痛み
#痛みの場所別チェック
#つま先立ちの違和感
#神経の圧迫
#靴の見直しポイント
3.日常生活の中に潜む「痛みの引き金」になる習慣とは?

クッション性のない靴、履いてませんか?
「普段スニーカー履いてるから大丈夫」と思っていても、実はソールがすり減っていたり、クッション性が落ちていたりするケースって少なくないんです。
とくに足の裏の外側が痛むときは、地面との衝撃をうまく吸収できていない状態かもしれません。薄いサンダルや硬めの革靴なども、長時間履いているとじわじわと足裏に負担がかかると言われています。
ちょっとした買い物や散歩でも、靴のタイプによって足の疲れ方は大きく変わることがあるそうです。
立ちっぱなし・動きすぎ、意外と足にきてるかも
「仕事でずっと立ちっぱなし」「スポーツを週4でやってる」――そんな方にこそ知ってほしいのが、繰り返しの動作が足裏の一部に負担を集中させるという考え方です。
特に、外側に体重がかかるクセがある人は、同じ場所を酷使してしまって痛みにつながる可能性があるとも言われています【引用元:https://tokyo-seikeigeka.jp/blog/17415/】。
その場では「ちょっと疲れただけかな」と思っていても、実は蓄積されたストレスだった…なんてこともあるかもしれません。
歩き方や体重のかけ方にクセがあることも
「まっすぐ歩いてるつもりなんだけど…」という方も、実は左右どちらかに偏って歩いていることがあります。
歩き方や姿勢のクセは、自分では気づきにくいもの。たとえば、足の外側に重心が偏る「回外歩行」などの傾向があると、足裏の一部分ばかりに負荷がかかるとも指摘されています【引用元:https://takada-seikei.jp/column/ashinoitami-mortonbyo.html】。
鏡の前で立ってみたり、足型をチェックしたりして、自分の重心バランスを見直してみるのもひとつの方法かもしれません。
加齢や筋力の低下も影響すると言われています
年齢を重ねると、自然と足裏の筋力や柔軟性が落ちてくることがあります。特にアーチ構造を支える筋肉が弱くなると、外側の部分に過剰な負荷がかかりやすいとも言われているようです。
「最近、足が疲れやすくなったかも…」と感じる方は、こうした体の変化が背景にある可能性も。無理をせず、自分の足にやさしい生活を意識することが大切です。
#足の負担習慣
#クッション性のある靴
#体重バランス
#歩き方のクセ
#足の筋力低下
4.足の裏の外側が痛いときに自宅でできる対処法

靴の見直しとインソール活用で負担を軽減
「足に合ってると思ってた靴が、実は合ってないかも…」
そんなことって、意外とありますよね。特に足の裏の外側が痛む場合は、クッション性が乏しかったり、足の形と靴のフィット感がズレていたりすると負担が集中しやすいと言われています【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4632/】。
柔らかいインソールを入れるだけでも、衝撃が吸収されやすくなって足裏が楽になるケースもあるそうです。足のアーチに沿った形状の中敷きがサポートになることもあります。
ストレッチやセルフマッサージを取り入れてみよう
「マッサージって自分でやって大丈夫なの?」と不安な方もいるかもしれませんが、無理のない範囲で行うことでリラックス効果が期待できるとも言われています。
たとえば、足の裏をテニスボールで優しく転がしたり、ふくらはぎを軽く伸ばしたりするだけでも、筋肉の緊張を和らげることにつながるようです【引用元:https://takada-seikei.jp/column/ashinoitami-mortonbyo.html】。
ポイントは「気持ちいい」と感じる程度で止めること。痛みが強まるようなら中止してくださいね。
冷やす?温める?状況によって使い分けを
「冷やしたほうがいいの?それとも温める?」
これもよくある疑問です。基本的には、炎症や腫れを感じるときには冷やすことがすすめられており、逆に慢性的な疲労感や血行不良が気になるときは温めると良いとされています【引用元:https://tokyo-seikeigeka.jp/blog/17415/】。
ただし、どちらが合っているかは痛みのタイプによって異なるため、試しながら体の反応を見ていくことが大切です。
痛みが強いときは安静を意識して
「動かないと悪化するんじゃない?」と心配になる気持ちもわかりますが、痛みが強いときは無理をせず安静にしたほうがよいとも言われています。
特に、歩行時にズキズキとした痛みがあるときは、いったん休んで足への負担を減らすことが改善への第一歩になることも。
一日だけでも座って過ごす時間を増やしたり、足を少し高くして休めるだけでも変化が出る場合があるようです。
#足裏ケア
#ストレッチとマッサージ
#冷やす温めるの使い分け
#インソールの工夫
#足の負担軽減法
5.病気が隠れているケースも|受診すべきタイミングと診療科の目安
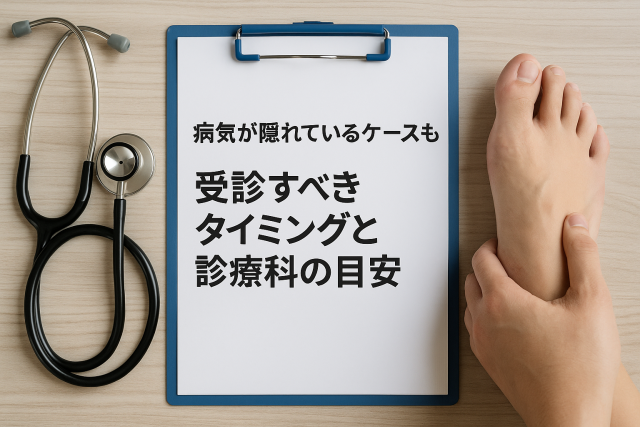
こんな症状が続くときは注意が必要かもしれません
「足の裏の外側が痛いだけだし、ちょっと様子見ようかな…」
そう思っていても、次第に痛みが強くなったり、しびれや感覚異常が出てきたりすると、少し話は変わってきます。
とくに以下のようなケースでは、何らかの疾患が関係している可能性があるとも言われています【引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4632/】。
-
数日たっても痛みが引かない
-
足の一部にピリピリとした違和感やしびれが出る
-
歩くと強い痛みが走る
このようなサインが見られるときは、専門機関で状態を確認してもらうことがすすめられる場合があります。
整形外科ではどんな検査をするの?
「行ってみたいけど、何されるんだろう…」と不安な方もいますよね。
整形外科では、まず問診や触診によって痛みの出る部位やタイミングを確認していく流れが多いようです。
必要に応じて、レントゲンやMRIなどの画像検査が行われ、筋肉・腱・骨・神経といった複数の構造を対象に調べていくそうです【引用元:https://takada-seikei.jp/column/ashinoitami-mortonbyo.html】。
「この痛み、単なる疲れじゃなかったかも…」と感じたら、無理せず来院することもひとつの選択肢です。
スムーズに伝えるために記録をとっておこう
「病院でうまく説明できるか自信ない…」という声もよくあります。そんなときは、痛みの状況をメモしておくのが役立つとされています。
たとえば、
-
どこが、どんなふうに痛むのか(ズキズキ、ジンジンなど)
-
いつから痛みが出たか
-
どんな動作で痛みが強くなるか
など、簡単でもいいので記録しておくことで、専門家に状況を的確に伝えやすくなるでしょう。
#足の痛みと病気の関係
#来院の目安
#しびれや感覚異常
#整形外科の検査内容
#症状記録のポイント







お電話ありがとうございます、
武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。