【記事構成】
1. 腕を上げると肩が痛い…まずチェックすべきこと
・どの動作で痛みが出るか(前方挙上/側方挙上/外旋など)
・発症時期、経過、痛みの性質(ズキッ/ジンジン/しびれ感など)
・他の部位の症状(首・肩甲骨・腕など)
2. 「腕を上げると肩が痛い」主な原因と特徴
・肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)
・腱板損傷(腱板断裂・腱板炎)
・インピンジメント症候群(肩峰下インピンジメント)
・石灰沈着性腱板炎
・上腕二頭筋長頭腱炎
・頚椎性(首由来の神経痛・頚椎症)
3. 症状の特徴・見分け方(セルフチェック)
・痛みが強い角度、痛みが和らぐ角度の違い
・夜間痛や安静時痛の有無
・可動域制限の有無
・首を動かすと変化するかどうか
・痛みの出方のタイミング(急に、徐々に、動作で出る)
・受診すべきサイン(腫れ・熱感・脱力など)
4. 病院での診断・治療の流れと選択肢
・整形外科受診の目安と準備する情報(症状経過、痛みの出る動きなど)
・診断手法(問診・触診、レントゲン、MRI、超音波検査 等)
・保存療法(薬・注射・物理療法・リハビリ)
・手術適応となるケース(腱板断裂、拘縮強い五十肩など)
・治療の注意点、よくある流れ
5. セルフケア・予防・改善ストレッチ・運動法
・痛みが強い時期にしてよいこと・避けること(安静 vs 過度な動かし方)
・段階別リハビリ・可動域拡張ストレッチの具体例
・肩甲骨周囲筋(棘下筋・棘上筋・肩甲下筋など)を整える体操
・姿勢改善・日常生活での注意点(デスクワーク、荷物持ち上げなど)
・再発防止のための習慣づくり
1. 腕を上げると肩が痛い…まずチェックすべきこと

動作ごとの痛みの確認
「横にだけ上げるとズキッとする」「前に上げると重だるい」など、人によって現れ方はさまざまです。どの角度で痛みが強くなるかを把握することで、五十肩なのか、腱板損傷なのか、あるいは首から来ているのかといった見当をつけやすくなります。
発症時期や経過の整理
痛みが急に出たのか、それともじわじわ強くなってきたのかを思い返してみましょう。急に激しく痛んだ場合は腱板損傷なども疑われますし、徐々に動かしづらくなってきた場合は肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)が多い傾向があります。
痛みの性質を見極める
「ズキズキと鋭い」「ジンジンとしびれるよう」「動かすと突っ張る」など、痛みの感じ方にも種類があります。鋭い痛みは炎症や損傷、しびれ感は神経の関与が考えられるなど、性質を伝えることは重要な情報になります。
#肩の痛み
#腕を上げると痛い
#セルフチェック
#原因の手がかり
#早めの対応
2. 「腕を上げると肩が痛い」主な原因と特徴

肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)
中年以降によく見られるもので、肩が固まったように動かしづらくなります。特に夜間の痛みが強く、眠れないと訴える方も少なくありません。「急に腕が上がらなくなった」という場合、このケースが多いです。
腱板損傷(腱板断裂・腱板炎)
肩の奥にある腱板という組織が傷つく状態です。物を持ち上げたり、頭の上に手を伸ばすと強い痛みを感じやすいのが特徴。野球やテニスなど、肩を酷使するスポーツ経験がある方に多いと言われます。
インピンジメント症候群(肩峰下インピンジメント)
「挟み込み」が起こるタイプの障害です。肩を横から上に上げるときにズキッとするのが典型的なサイン。「最初は違和感だけだったのに、次第に痛みが強まった」という声もよく耳にします。
石灰沈着性腱板炎
腱板に石灰がたまり、急激に炎症が起こることで強烈な痛みを感じるものです。発作的に痛みが出て腕を動かせなくなることもあり、「何もしていないのに急に痛くなった」と驚く方もいます。
上腕二頭筋長頭腱炎
力こぶの筋肉を支える腱が炎症を起こす状態。前方に手を伸ばすと痛みが強まり、日常のちょっとした動作でも不快感が続くのが特徴です。
#肩の痛み
#腕が上がらない
#四十肩五十肩
#腱板損傷
#首からくる痛み
3. 症状の特徴・見分け方(セルフチェック)
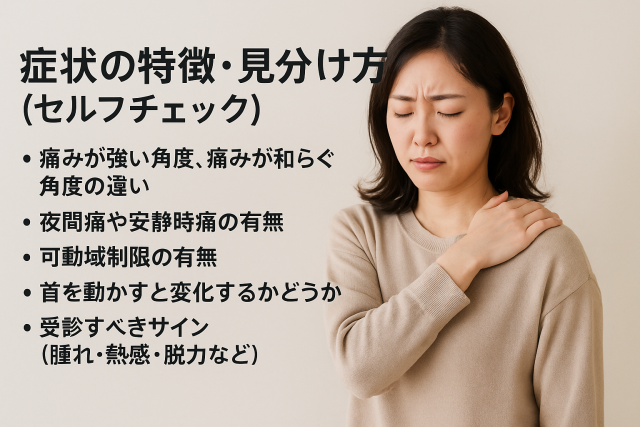
痛みが強い角度・和らぐ角度の違い
肩や首に不調を感じるとき、「どの角度で痛みが強まるのか」を確認することは大切です。例えば、腕を横から上げると強い痛みが出るのに、前に上げると比較的楽に動かせるといった違いがあります。この角度差は、炎症がある部位や関節の動きに影響している可能性を示すサインになります。
夜間痛や安静時の痛み
夜にズキズキして眠れない、安静にしているのにジワジワ痛む、といった「夜間痛」や「安静時痛」がある場合は要注意です。日中の動きに関係なく痛みが続くときは、炎症が進んでいる可能性もあり、早めの相談が望ましいです。
可動域制限の有無
「ここまでしか腕が上がらない」と感じるような可動域の制限は、腱板損傷や関節周囲炎などで見られる典型的な特徴です。左右差を比べてみると、自分では気づいていなかった制限が明確になることもあります。
痛みの出方のタイミング
急に「ピキッ」とした痛みが出たのか、それとも徐々に重だるさが強まってきたのか。発症の仕方によっても原因は異なります。スポーツや荷物を持ち上げた直後に起こる急性痛と、デスクワークで少しずつ悪化する慢性痛では、背景の要因が違ってきます。
来院を検討すべきサイン
肩や腕に腫れ・熱感・脱力が出てきた場合は、自分で様子を見るのではなく来院を検討すべきです。とくに腕に力が入らない、夜も眠れないほど痛む、といった状態は早めの相談が安心につながります。
#肩の痛みセルフチェック
#夜間痛と安静時痛
#可動域制限の見分け方
#首との関連サイン
#来院の目安
4. 病院での診断・治療の流れと選択肢

整形外科に来院する目安と準備
「肩の痛みが長引いているけど、病院に行くべきかな?」と悩む方は多いと思います。日常動作で痛みが強まる、夜眠れないほどの痛みがある、動きが制限されているといった場合は、整形外科に相談するのが一般的な流れです。来院の際には、いつから痛みが始まったか、どの動作で痛みが出るのか、経過や強弱の変化を整理して伝えると検査がスムーズになります。
治療を受ける際の注意点
治療の流れは人によって異なりますが、一般的には「診察 → 画像検査 → 保存療法 → 経過観察」という流れをたどります。大切なのは、焦らず継続して取り組むこと。また、医師やリハビリスタッフとよく相談し、自分の生活スタイルに合った改善プランを一緒に作っていく姿勢が求められます。
#肩の痛み
#整形外科の検査
#保存療法とリハビリ
#手術が必要なケース
#改善の流れ
5. セルフケア・予防・改善ストレッチ・運動法

痛みが強いときに避けること・してよいこと
「肩が痛いときって、安静にした方がいいの?」とよく聞かれます。答えは、完全に動かさないよりも“無理なく動かす”ことが大切です。炎症が強い時期は、激しいストレッチや重い荷物を持つ動作は避けましょう。その一方で、腕を軽く振る・温めるなどは血流を保つのに役立ちます。
段階別リハビリとストレッチ
「痛みが和らいできたらどうすれば?」という声も多いです。まずは可動域を広げるストレッチから。壁を使った前方挙上や、タオルを背中で持って肩を引き伸ばす動きが有効です。慣れてきたら、チューブを使った軽い負荷トレーニングに進めると回復がスムーズにつながります。
肩甲骨周囲の筋肉を整える体操
肩は肩甲骨まわりの筋肉が大きく関わります。棘上筋・棘下筋・肩甲下筋などを意識する簡単な運動があります。例えば、肩甲骨を寄せる“肩すくめ運動”や、うつ伏せで腕を軽く上げるエクササイズは無理なく取り入れられます。
姿勢改善と日常での注意
「デスクワーク中に肩が重くなる」という方は、長時間同じ姿勢を避ける工夫が大切です。30分に一度は首や肩を回すだけでも違います。また、荷物を持ち上げるときは腰だけでなく膝を使う意識をすると肩の負担を減らせます。
再発防止のための習慣づくり
改善した後こそ、再発を防ぐ習慣が必要です。毎日のストレッチを短時間でも続けること、睡眠や栄養バランスを整えることが肩の安定につながります。少しの積み重ねが、長い目で見て大きな差を生みます。
#肩のセルフケア
#肩甲骨体操
#姿勢改善のコツ
#肩の再発防止
#段階別リハビリ
この記事に関する関連記事
- 50肩 原因とは?突然肩が上がらなくなる理由と放置リスクを専門家が解説
- 四十肩 治し方|痛みを改善し再発を防ぐ完全ガイド
- 肩こり ストレッチ 即効|たった数分で軽くなる原因別メソッドと正しいやり方
- 左肩から腕が痛い 原因|放置NGの症状と考えられる疾患・対処法を専門家がわかりやすく解説
- 肩こり 重症度 チェック|セルフで分かる4段階&早めの対処ガイド
- 肩甲骨の上が痛いときに知っておきたい原因と対処法|早くラクになる完全ガイド
- 肩の付け根が痛い ズキズキ:20代で起こる原因とすぐできる対処法
- 「肩の付け根が痛い」原因と対処法|ズキズキ痛む痛みをやわらげるために知るべき5つのステップ
- 上を向くと肩が痛い 治し方|原因別にすぐできるセルフケアと受診タイミング
- 肩こり 治し方:デスクワーク・姿勢・ストレス対策を徹底解説
- 「肩が重い」と感じる原因と今すぐできる対処法|専門家が徹底解説
- 肩 張ってる時に試したい!今すぐ楽になる原因と対処法
- 五十肩 治し方|自宅でできる対処法と病院での治療法をわかりやすく解説
- 六十肩の痛みを感じたら?原因と正しい対処法を徹底解説
- 肩こり 対処法|今すぐできる5つのセルフケアでつらい痛みを解消
- 整体 肩こり|専門家が解説する原因と改善方法







お電話ありがとうございます、
武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。