【記事構成】
1 なぜ「起きると吐き気」で「寝ると楽」なのか?
寝ている間と起きた後の体の変化(自律神経/血流)
胃酸・逆流・重力の影響で起きる吐き気
起き上がり・立ち上がり時の体位変化(起立性低血圧など)
2「起きると吐き気」が起こりやすい生活・習慣パターン
夜遅い食事・脂っこい食事・寝る直前の飲食
睡眠の質・寝姿勢・枕の高さなど寝る時の環境
ストレス・睡眠不足・自律神経の乱れ
3 自宅でできる簡単セルフケア/改善策
寝る姿勢・枕・ベッドの調整
起床直後の動作をゆっくりにする・立ち上がりの工夫
食事・飲酒・カフェイン・就寝2〜3時間前の注意
ストレス軽減・規則正しい生活リズム・睡眠環境の改善
4 どんなときに「受診/検査」を考えるべきか?
吐き気が数日続く・体重減少・血便・胸焼け・呑酸などがある場合
疑われる疾患:逆流性食道炎・機能性ディスペプシア・起立性低血圧など
5 まとめ:起きると吐き気 寝ると楽、まずは“生活習慣の見直し”から始めよう
早速できる3つのアクション(例:枕を少し高く・起床時ゆっくり動く・夜食控える)
継続しても改善しないなら次のステップへ
1 なぜ「起きると吐き気」で「寝ると楽」なのか?
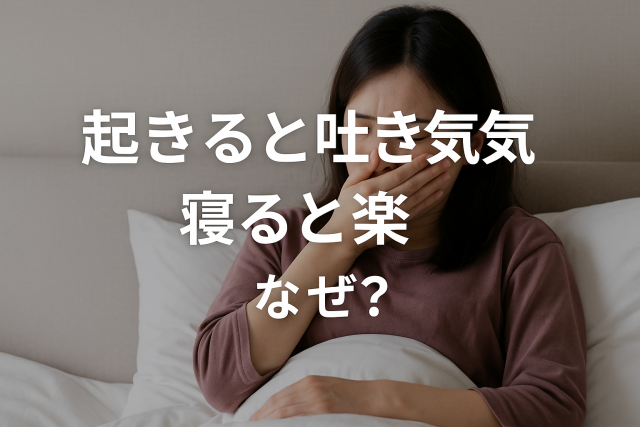
寝ている間と起きた後の体の変化(自律神経/血流)
「寝ている時って体は休んでいるのに、なんで朝だけ吐き気が出るの?」
こんな疑問を持つ方も多いはずです。
実は、寝ている間は“副交感神経”が優位になって体がリラックスモードになっています。そこから起きた瞬間、急に交感神経が働き始めるので、体の切り替えにうまくついていけない人は、血圧や血流が安定せず、気持ち悪さにつながりやすいんですね。
「寝ている時は楽なのに、立つとしんどい…」
これは、自律神経の切り替えがスムーズにいかないタイプの人に起こりやすい反応でもあります。
胃酸・逆流・重力の影響で起きる吐き気
もう一つ、よくあるパターンが胃酸関連のもの。
横になっている時は胃酸が上がりにくいのですが、起きると重力が働いて胃の内容物が動きやすくなり、その刺激で“ムカッ…”とくることがあります。
特に、
・夜遅くに食事をした
・脂っこいものを食べた
・胃もたれしやすい
こういった人は、朝に吐き気を感じるケースが多いですね。
起き上がり・立ち上がり時の体位変化(起立性低血圧など)
布団からパッと起きた瞬間に“クラッ”“ウッ”とくる感じ、ありませんか?
これは体の血圧調整が追いついていない「起立性低血圧」という状態の可能性もあります。
横から立つまでの変化が急すぎると、一時的に脳への血流が少なくなり、めまいや吐き気につながることがあります。
実際、
「朝はゆっくり起きた方が楽だった」
という方は、このタイプが多いですね。
#朝の吐き気
#寝ると楽
#自律神経の乱れ
#胃酸逆流
#起立性低血圧
2「起きると吐き気」が起こりやすい生活・習慣パターン

夜遅い食事・脂っこい食事・寝る直前の飲食
「昨日の夜、遅い時間に食べちゃったんだよね…」
そんな時に限って、翌朝の胃がスッキリしないことがあります。
人によって感じ方は違いますが、深夜の食事や脂っこいメニューは胃に残りやすく、寝ている間に消化が追いつかないことがあるんです。
そして、「寝る前にちょっとだけ…」とつまんだ一口でも、横になると胃酸が戻りやすくなるので、朝に気持ち悪さにつながることがあります。話してみると「確かに思い当たるかも…」という声も多いところです。
寝姿勢・枕の高さ・寝る時の環境
「枕が合ってないのかな…?」
実はこれ、よくある相談なんです。枕が高すぎたり、寝返りがしづらい姿勢だと、首まわりの緊張が強くなりやすく、朝の不快感につながることがあります。
また、睡眠の質そのものが落ちている場合も、翌朝の気分に影響しやすいと言われています。部屋の明るさや温度など、気づかない小さな刺激で眠りが浅くなるケースもあります。
ストレス・睡眠不足・自律神経の乱れ
「最近ちょっと疲れてるかも…」
そんな時、朝の吐き気を訴える方も少なくありません。ストレスが続くと自律神経が乱れやすく、胃の働きが不安定になることがあります。
睡眠不足も同じで、朝になると体がうまく切り替わらず、軽い気持ち悪さとして出ることがあります。「心と体のリズムがズレている感じ」と表現される方もいます。
#起きると吐き気
#生活習慣の影響
#睡眠環境
#自律神経の乱れ
#朝の不快感対策
3 自宅でできる簡単セルフケア/改善策

寝る姿勢・枕・ベッドの調整
「まず寝る姿勢ってどうしても大事なんですよね」とお伝えすると、多くの方が枕の高さを気にしています。
高すぎても低すぎても首が緊張しやすく、起きたときのだるさや吐き気とつながりやすいので、首の角度が自然になる高さを探すのがポイントです。
ベッドの硬さも関係していて、柔らかすぎると腰が沈みやすく、朝の不快感が強くなる場合があります。
起床直後の動作をゆっくりにする・立ち上がりの工夫
「朝って起き上がる瞬間が一番つらいんですよね」と言われることがよくあります。
実は体がまだ“朝モード”に切り替わっていないので、いきなり起きると血流が追いつかず、ふらつきや気持ち悪さが出やすいんです。
布団の中で背伸び→ゆっくり横向き→手をついて上体を起こす。この順番を意識すると、かなり楽になりますよ。
食事・飲酒・カフェイン・就寝2〜3時間前の注意
「夜遅くに食べちゃうんですよね」という相談は本当に多いです。
胃が動き続けたまま寝ると、逆流感や胸焼けが出て、翌朝の吐き気につながることがあります。
飲酒やカフェインも寝付きや睡眠の質に影響するので、就寝2〜3時間前は控えると翌朝のスッキリ感が変わります。
ストレス軽減・生活リズム・睡眠環境の改善
気付かれにくいポイントですが、「ストレスが続くと朝いちの不快感が強まりやすい」こともあります。
自律神経が乱れると、胃腸の動きや睡眠リズムに影響するため、軽い深呼吸や入浴で気持ちを落ち着ける時間を作ると良い方向に向かいやすいです。
部屋の明るさや室温など、睡眠環境を整えるだけでも朝の状態が変わる方は多いですね。
#朝の吐き気ケア
#寝姿勢チェック
#起床動作の工夫
#就寝前の生活改善
#ストレスと自律神経
4 どんなときに「受診/検査」を考えるべきか?

吐き気が数日続くときは一度チェックを
「1~2日で落ち着くかな」と思っていたのに、気づいたら数日同じような状態が続いている…そんなケースは、体のどこかに負担がかかっているサインとして捉えておくと安心です。とくに、食事が普段より入りづらい、ふわっとする感覚がある、朝起きるたびに気持ち悪さが増している、こんな状態なら専門家に相談して状況を整理してもらうと良い方向に向かいやすくなります。
体重減少・胸焼け・呑酸・血便などがある場合
「最近なんとなく食欲が落ちて体重が減っている気がする」
「胸のあたりがムカッとして、すっぱい感じが上がってくる」
「便に赤みや黒さが混じる気がする」
こうした変化は、胃や食道のトラブルが影響していることがあります。逆流性食道炎のように、胃酸が上がりやすい状態が続くと吐き気・胸焼け・呑酸がセットで起こりやすくなりますし、機能性ディスペプシアのようにストレスや自律神経が関係して胃が働きづらくなるケースも少なくありません。
起立性低血圧が関係するケースもある
朝に多い “ふらっと感” や “立ち上がったときの気持ち悪さ” は、起立性低血圧が関係することもあります。
「寝ている時はなんともないのに、起き上がると気持ち悪さが出る」
といった相談は実際に多く、血流が急に変化することで吐き気が出ている可能性があります。
体質や生活リズムが影響しているケースもあるため、無理に我慢せず、一度プロに状況をみてもらうと安心につながります。
#吐き気のサイン
#検査を考える目安
#逆流性食道炎の可能性
#起立性低血圧との関係
#数日続く症状は相談を
5 まとめ:起きると吐き気 寝ると楽、まずは“生活習慣の見直し”から始めよう
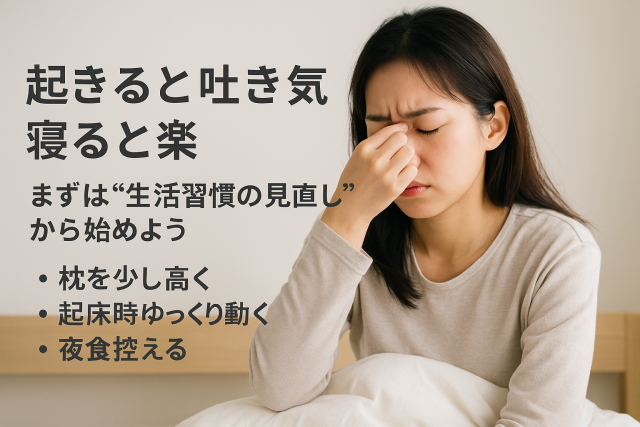
今日からできる3つのアクション
Aさん「起きると吐き気がするんだけど、何から変えたらいいんだろう?」
私「まずはシンプルなところからで大丈夫ですよ。例えば、枕を少し高くして眠るのも一つです。胃の位置が下がって、朝のムカムカが軽くなりやすいんです。」
Aさん「なるほど。他には?」
私「起きる時の“動き方”も大事です。布団からいきなり起き上がると、自律神経が急に切り替わって吐き気が出やすくなるので、横向き→手で支えながら→ゆっくり起きる、の順で動いてみてください。」
Aさん「たしかに、バッと起きるクセがあるかも…。夜は?」
私「夜食や脂っこい料理、カフェインが遅い時間に入ると、胃がずっと働き続けて朝の不調につながることもあるんです。寝る2〜3時間前は少し控えると、翌朝がラクになりやすいですね。」
もし続くなら、次のステップへ
生活習慣を見直しても数日〜数週間ほど変化がない場合は、別の原因が隠れていることもあります。
そんな時は無理をせず、専門家に見てもらうのも一つの方法です。体の状態を確認してもらうことで「何が起きているのか」を客観的に整理できますし、改善につながるヒントが見つかることも多いです。
#起きると吐き気
#寝ると楽
#生活習慣の見直し
#朝の不調ケア
#自律神経サポート







お電話ありがとうございます、
武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。